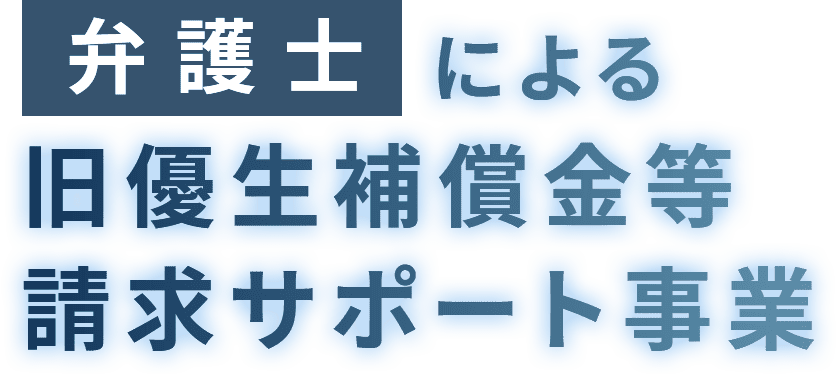Q&A
対象:弁護士
- Q
委託決定通知書が交付されてから相談者と接触するのか、交付前に接触して良いのか。
- A
委嘱決定通知書の交付前であっても選定報告書の「選定日」以降であれば業務の対象になります。
- Q
都道府県から選定されたが、この後の流れを教えてほしい。
- A
弁護士から弁護士会へ「サポート弁護士同意書(以下「同意書」といいます。)」をご提出ください。同意書の確認ができましたら、事務センターから委嘱決定通知書と報告書の書式を送付します。
- Q
診断書作成費用は実費の対象となるか。
- A
診断書作成費用については、請求者の請求が認定された場合に国が補償金等と併せてお支払いをするので、本事業の実費の対象からは外れます。
- Q
証明書等の取り寄せ費用は実費の対象となるか。
- A
証明書の取り寄せ費用については対象となります。
- Q
請求者が弁護士事務所へ来る際のタクシー代は実費の対象となるか。
- A
対象外となります。なお、弁護士が請求者宅に行く場合のタクシー代は実費の対象となります。
- Q
ガソリン代はどのように算出すればよいか。
- A
業務報告書の【5.実費】 の「金額欄」に1km当たり37円で計算した金額を記載してください。
- Q
請求者と弁護士との契約書の取り交わしは必要か。
- A
請求サポート業務を行うに当たり、請求者と弁護士との間での契約書の取り交わしは不要です。
- Q
「業務報告書」を作成する時間は報酬の対象になるか。
- A
対象外となります。
- Q
手話通訳者へは、サポート弁護士が立て替えて支払ったうえ、精算事務センターへ領収書を添えて請求する、という流れになるのか。
- A
弁護士様が現金でお立替の場合は手話通訳者への支払証憑(領収書等)を送付してください。請求書にて振込処理された場合は請求書と振込証憑をお願いいたします。
対象:弁護士会
- Q
弁護士からの同意書の取得について、同意を取ることは必須であるか。
- A
同意書の確認ができない場合は、委嘱決定通知書の送付ができないので、必ず同意書を取得してください。なお、一度報告いただければ都度確認させていただくことはありません。
対象:都道府県
- Q
請求者が夫婦2人とも対象者となっていて、同じ弁護士を選定した。
その場合の報酬は、別々に請求してもらう形でよいか。
- A
①夫が手術を受けた本人、妻が特定配偶者の場合、案件としては1件とみなします。
②夫が手術を受けた本人、妻も手術を受けた本人の場合、案件としては2件とみなします。
- Q
選定報告書は一定期間ごとに提出する形でも良いか。
- A
選定報告書を事務センターにいただかないと委嘱決定通知書が送付できないため、早々に送付ください。
- Q
相談者(請求者とは別)から相談があった時点で弁護士を紹介しており、請求者の情報を把握していない。
そのため、選定報告通知書に請求者の情報を記載できないが、空欄でもよいか。
- A
委嘱決定通知書の作成や事務センターにおける案件管理に用いるため、弁護士等に確認したうえで請求者の情報を記載し、選定報告書を事務センターへ送付してください。